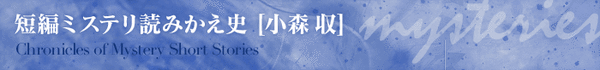
「鞭打たれた犬たちのうめき」が、1973年のMWA賞を取って、すぐにミステリマガジンに訳された(1974年9月号)とき、私はハーラン・エリスンという名前を知りませんでした。すでにアメリカSF界では知らぬ人はなく、日本でもSFファンの間では有名だったようですが、最初の邦訳書『世界の中心で愛を叫んだけもの』が出たのが、前年の73年です。実際には日本語版のマンハントに短編が載ったこともあるのですが、それが駄作だったことは以前に書きました。
ここ半年ばかりの間に取り上げた作家は、フレドリック・ブラウンを例外として、いかに、ミステリの読者に親しまれようと、ミステリマガジンに頻繁に登場しようと、SF作家であることは自他ともに認める大前提で、ミステリシーンの中で評価されたり、その歴史の中でとらえられるということはありません。しかし、ハーラン・エリスンは違います。50年代のミステリ雑誌の書き手であり、MWA賞の短編賞を「鞭打たれた犬たちのうめき」と「ソフト・モンキー」で二度も射止めた、まぎれもないクライムストーリイの作家なのです。
「鞭打たれた犬たちのうめき」は、ショッキングな始まり方をします。ニューヨークの高層アパートの中庭で、ひとりの女が殺される。主人公の女性は自室の窓のはるか下方で、まさに起きている殺人を目撃しますが、恐怖に声も出ません。しかも、周囲の窓には、その犯行を見下ろす人々が幾人も見えているのです。残忍な犯罪に対して周囲が無関心を決め込むことは、当時すでに社会心理学の研究対象になっていたほどで、ニューヨークの治安の悪さも、九州の田舎の高校生だった私でさえ漏れ聞いていました。それでも、警察に通報することもなく(しなくても、犯人は直後に警官に射殺されるのですが)、しかし、恐怖の体験は日常として残る。それを共通体験として、同じアパートの男と、彼女は知り合い、肉体関係を結びます。彼女はバーモントの有名女子大を出て、いまはダンスの記譜を仕事にしていますが、すぐに、彼と諍いをします。ニューヨークっ子の彼は、僅かな意見の相違にも辛辣な口をきき、彼女にあたり、アナルセックスを強要したのです。それが、ニューヨークというストレスに満ちた都市で生まれ育った結果であると、彼は強弁し、地方女子大出の彼女の頭の中が、お花畑でもあるかのように指弾します。自然、彼とは疎遠になりますが、そんなある日の留守中、彼女の部屋に強盗が侵入し、帰宅した彼女と鉢合わせします。命がけの格闘に否応なく巻き込まれた彼女は、ベランダから突き落とされそうになりながら、そこで、あるものを目撃し、彼の正しさに思いあたると同時に、ニューヨーカーの新しい神を見つけます。
初読時もそうでしたが、むき出しの暴力にさらされた都会の孤独と恐怖は、肌に迫るものがあります。ただし、十代の私が、なぜ、こういう結末になるのだろうと、訝しく思ったことは確かで、今回読み返しても、結末は釈然としません。共同幻想としても、それなら、なぜ、それがメンバーの安心と安全を保障するのかが分からない。本当に超越的な何かがあるのなら、ずいぶん安易で都合のいい超越者ではないでしょうか? それに、冒頭の殺人を見守る人々の心の中が一様だと言われて、はいそうですかと納得するほど、もう子どもでは、私もありませんからね。
「ソフト・モンキー」は、それに比べると、はるかに単純なクライムストーリイでした。ニューヨークの街頭で眠ろうとしていた、黒人のバッグレディ(家財一式をバッグに入れて持ち歩くホームレスの女性ですね)が、目の前で起きた殺人を目撃します。ギャングの抗争らしい殺しで、しかも、目撃したことを見とがめられ、自分も追われます。命からがら追手をくらまし、その事件を報じた新聞紙を身体に巻き付けた(暖かいのです)彼女は、すでに、黒人女性のホームレスがふたり殺されたことを知っています。目撃者の口止めのために、黒人女性というだけで手当たり次第に殺しているのです。やがて、彼女のところに殺しの手が伸びてくるのは、時間の問題であり、事実、殺し屋がやって来て……。
ここには、暴力と隣り合わせにニューヨークの底辺で生きる危うさが、確かに描かれてはいます。しかし「鞭打たれた犬たちのうめき」にあった、ひりひりするような恐怖はありません。そもそも、彼女の口封じを狙う男たちの行動に、いささか無理がある。殺しては、間違いだったと気づくのくり返しだったのでしょうか。だとしたら、ずいぶん愚かではないでしょうか。まあ、この結末では、少々ほのぼのとなってしまう(そのこと自体は、必ずしも悪いとは思いません)のは、無理のないところでしょう。
SF作家としてのハーラン・エリスンは、数多の受賞歴と多くの武勇伝的なゴシップとで、高名な存在でした。今年亡くなったエリスンを追悼する特集を組んだSFマガジンが、ちょうど出たところですが、その年譜を読めば、そのことがよく分かるでしょう。そして、MWA賞受賞の二編がそうであったように、残虐な暴力を描くことが、やはり多い。
SF作家としてのハーラン・エリスンは、数多の受賞歴と多くの武勇伝的なゴシップとで、高名な存在でした。今年亡くなったエリスンを追悼する特集を組んだSFマガジンが、ちょうど出たところですが、その年譜を読めば、そのことがよく分かるでしょう。そして、MWA賞受賞の二編がそうであったように、残虐な暴力を描くことが、やはり多い。
「世界の中心で愛を叫んだけもの」は、日本ではこれと題名が類似したというか、この題名をパクった小説がバカ売れしたために、エリスンの作品でもっとも名の知られるものとなりましたが、そんなこととは関係なく、おそらく世界じゅうでもっとも有名な彼の作品になっています。この一編には、エリスンの特徴が集約的に現われています。冒頭ではボルティモアのウィリアム・スタログという男の無軌道な大量殺人が語られます。以下、それぞれの関連が分からないままに、時空を超えた短いエピソードが連なっていきます。固有名詞の説明を廃したところ、「どの頭もらんらんと目を光らせ、待ち、餓え、狂っていた」というふうに、同じ品詞を重ねる(動詞のことが多いようです)といった、スタイルの面での特徴も顕著です。とくに、後者の多用はエリスンの文体の個性と言えるでしょう。
しかしながら、私には、この小説の示すヴィジョンが、よく分からない。愛と憎悪、暴力と平和といったものは、相反しないとか、ともに在るといった程度のことで良ければ、それは問題がないのですが、それなら、そう言ってしまった方が早い。私がエリスンのSFを読んで行きつくのは、大山鳴動鼠一匹。もっとも、その大山鳴動ぶりが面白いというだけでいいのなら、問題はありません。
たとえば「101号線の決闘」を、私は楽しく読みましたが、その対決のディテイルをスピーディに描写する疾走感が魅力ではありますが、未来の公認された決闘の話は、書かれた当時でさえ、平凡であったでしょうし、そこに新しい何かがつけ加わっているとは言えないでしょう。「サンタ・クロース対スパイダー」は、60年代に大流行したスパイアクションの愉快なパロディ以外の何物でもありませんでした。こうした大上段に振りかぶらない作品の中では「プリティ・マギー・マネーアイズ」を、私は推奨します。ラスヴェガスのカジノでツキを使い果たしたような主人公の男が、拾ったコインで最後の運試しをしたところ、スロットマシーンのジャックポットを出してしまう。この2000ドルをどのようにお使いで? と尋ねるカジノの男に、もう一度カジノに戻ることをにおわせて、逆に安心させてしまいます。戻れば、いずれ取り返せると、胴元は考えるのです。ところが、男はすぐにスロットマシーンでジャックポットを出し、のみならず、何度やってもジャックポットが出続けて……。途中で挿入される、プリティ・マギーのエピソードや謎めいた描写は最後に落ち着くところに落ち着きますが、そこのアイデアは、ありきたりでしょう。
しかしながら、エリスンを代表する作品ということになれば、たとえば「『悔い改めよ、ハーレクィン!』とチクタクマンはいった」とか「おれには口がない、それでもおれは叫ぶ」といったものになるのでしょう。前者の時間に遅れることで寿命が短縮されるというディストピアにしても、後者のコンピュータが人類を絶滅に追いやり、その果てに飼い殺すだけのために生かされているような登場人物たちという絶望の状況にしても、それを描くエリスンの筆は、才気を見せびらかすことに忙しくて、肝心の恐怖が伝わってきません。これは、先にあげたスタイル上の特徴、固有名詞――それも、かなり専門的な――の説明抜きの使用や、品詞の連打といった技巧が、描写に貢献せずに、見た目の華やかさだけに陥っていることも大きいと思います。状況描写に入るときに、一旦説明してから入ることがあるのも、描写を重くしている一因でしょう。ときに、文章の順番がおかしいのではないかと思うことさえあります。
「おれには口がない、それでもおれは叫ぶ」には、文中に、ときおりパンチングテープが挿入されていて、いまでは何のことやら通じないかもしれません。「プリティ・マギー・マネーアイズ」にも、奇をてらった表記が出て来ましたが、アルフレッド・ベスターにもっとも著しい、こういうタイポグラフィックな効果の新奇さが、いかに腐りやすいことか。これを「アルジャーノンに花束を」の日本語訳と比べてみてください。「アルジャーノンに花束を」は日本語にもっとも向いた作品ではないかと、私は考えているのですが、漢字かな交じりという特徴の持つタイポグラフィックな効果――字面そのものからチャーリイの変化が見て取れる――の前には、ベスターやエリスンの工夫は、単に本質をはずれた技巧の末路を示しているだけにしか見えません。
ハーラン・エリスンは、そのトラブルを顧みない、しかしキャッチーな言動と、おそらくは一途なSFへの愛情とで、SFシーンの伝説となりました。ハーラン・エリスンの本質は作家ではなく、アジテーターではないのかというのが、そして、エリスンの名は『危険なヴィジョン』の編者として残るのではないかというのが、遠目から眺めただけにすぎない私の感想です。
奇想天外は、1974年1月号として73年の暮れに盛光社から創刊されました。旧・奇想天外あるいは第一期奇想天外と呼ばれるもので、同年10月号までで休刊し、数か月のブランクを経て、同じ誌名で復活します。復活後の同誌が、SF専門誌に特化したのに対して、旧・奇想天外はSFとミステリを中心に、ファンタジー、ホラー、ノンフィクションと間口を広く取っていました。その7月号の巻頭に掲載されたのが、ゼナ・ヘンダースンの「静かに!」(「しーッ!」)でした。以後、休刊までに「おいでワゴン!」(「おいで、ワゴン!」)と「ページをめくると」(「ページをめくれば」)のと、三つの短編が掲載されました。私は、初対面のこの作家の短編がいたく気に入って、同級生の女の子に勧めたところ「ピープルシリーズの人でしょう?」とあっさり言われました。私が知らなかっただけで、SFの読者には人気のシリーズなのでした。
三編とも50年代の作品で、当時から見ても、ふた昔前の小説でした。「静かに!」は、喘息の男の子とベビーシッターに来ている娘のやりとりから始まります。女の子は幾何の宿題をやらねばならないのですが、男の子はうるさくしてばかりいる。そこで、その子の好きな空想あそびをして、興がのったところで、あとは自分ひとりでやりなさいと、宿題に戻ります。ところが、男の子は、一人遊びで本当にはないものを想像したら本当になっちゃったと言い出して、しかも、あらゆる音を吸い取る電気掃除機に似た得体のしれない何物かが現われます。「おいでワゴン!」は、子ども嫌いを自称する語り手が、奇妙な甥の話をします。この子が手押しのワゴンに向かって「おいで」と言うと、ワゴンがひとりで動いてしまうのを、語り手が目撃し、以来、まわりの大人は誰一人気づかないうちに、この男の子は不思議な力を発揮するのでした。どちらの小説も、ファンタジーとして独創的なアイデアとは言い難いでしょう。しかし、前者では、ユーモラスで不気味な怪物が、少しずつ、その本性が予想外に破滅的なことを示していく過程が巧みに描かれ、結末も鮮やかでした。後者はクライマックスで起きる事件で、語り手と少年の関係が抜き差しならなくなるのがよく、男の子の無邪気さ、超能力が本当にあるのかという疑惑を、巧みに用いて、一種のリドルストーリイになっていました。「ページをめくると」は、このふたつとはいささか趣きが異なり、小学校の最初の先生の魔法のような授業を、主人公の女性が回想する物語です。ファンタスティックな授業を、おそらくは一生の指針にしたであろう語り手の女性が、同窓会で迎える一景に向けて、静かに小説は進んでいきます。
今回読み返してみて、「おいでワゴン!」が、もっとも良く出来ていると思いましたが、いずれも、渋い佳作で、この作家の実力は、やはり相当なものだと思いました。
ゼナ・ヘンダースンは、このところ読んできたSF作家に比べると、一般的な評価は低い――と言って言い過ぎなら、それほど重きを置かれてはいないでしょう。しかし、わずか10か月で消えてしまったユニークな雑誌が、私に教えてくれた最高の作家が、このゼナ・ヘンダースンであったことは確かです。他とのバランスを失して、ヘンダースンのこの三編を取りあげたのは、そのことを書き留めておきたかったからです。この三つの短編は2006年に刊行されたゼナ・ヘンダースン短編集『ページをめくれば』に、どれも改訳されたものが収められています。
※EQMMコンテストの受賞作リスト(最終更新:2014年11月5日)





