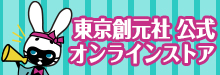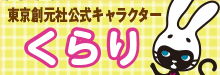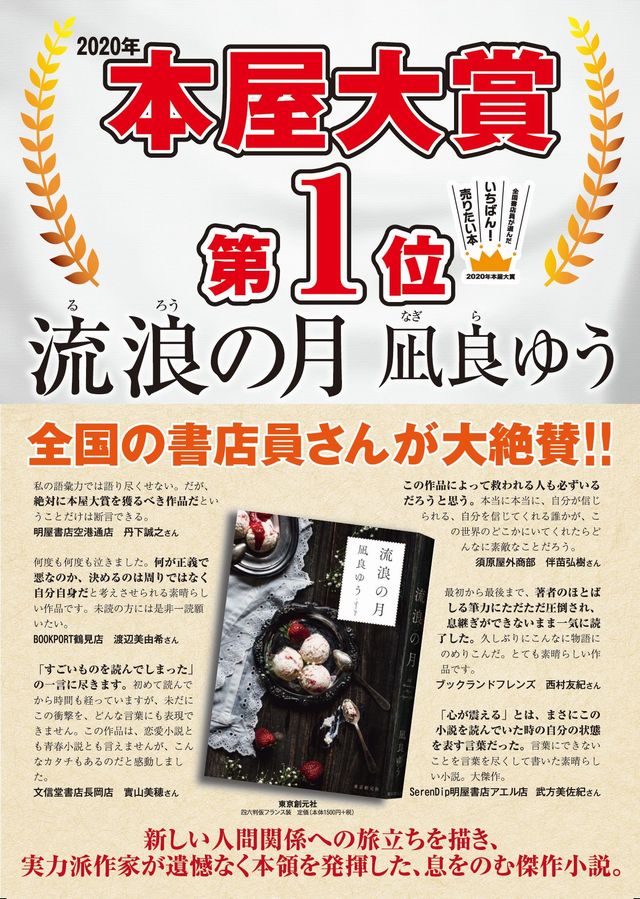蜃気楼のごとく姿を消した謎の青年芸術家、藤江恭一郎。
彼の手になる仮面をめぐり各地で事件が頻発する。
怪異とサスペンス、仮面づくしの連作短編ミステリ、連載開始。

前口上
吉祥寺駅の南口から井の頭公園を通り抜けて低い土手を上ると、碁盤の目に路地の入り組んだ品のよい住宅街が広がっている。住所でいうと、このあたりは三鷹市井の頭である。これを西へ向かえば、知らず識らずにまた広大な井の頭公園に呑みこまれることになり、所は武蔵野市御殿山と変ずる。一般に「武蔵野」の響きからイメージされる雑木林は、吉祥寺周辺ではこの御殿山の公園敷地内に美しい姿の大半を留めるのみだが、じつは吉祥寺通りをくだって自然文化園を過ぎた先の目立たぬ一角にも、丈高な雑木林の残る秘密めいた土地がある。
その小暗い木立のなか、いかにも人目を避けるような風情で、ささやかな洋館が潜んでいるのだった。白壁にフランス瓦の赤い三角屋根をいただき、周囲の環境も相まって、どことなく別荘然、四阿【あずまや】然として見える一軒家である。この淋しい家の存在を知る者は少ないが、さらにそこの住人、全身を黒衣に包み、鉄の仮面をかぶった異様な人物については、近隣の住民ですら見かけた者は稀であろう。
すこし前、藤江恭一郎という若き芸術家がいた。
知名度は低く、発表作品も多くないが、独特の個性を持つ仮面作家として一部で評価の高まりつつあった青年だ。
藤江が作品づくりに好んで用いた素材、それが鉄である。鍛鉄【ロートアイアン】。コークスを焚いて鉄を熱し、ハンマーで叩きのめし、火花を散らしてバーナーで焼き切る。やがて最後の工程において表面を埋め尽くす点描のごとき鎚目【つちめ】は、冷たく硬い鉄仮面に命を吹きこみ、あたかも人肌と見紛うほどの質感さえもたらすのだった。
仮面作家としての藤江恭一郎の活動期間はごく短かった。工房における不幸な事故が、彼の芸術家生命を奪ったのだといわれている。
ところで、蜃気楼のように姿を消したこの若き芸術家に関し、以前からまことしやかに囁かれている噂があった。
いわく、藤江恭一郎の手になる作品には呪いが籠められているとの一種の怪談で、いかにも眉唾ものの話だが、事実、彼の生みだした仮面にまつわる奇怪な出来事が、さまざまな場所でたしかにいくつも起こっていた。
第一話 訪問者
1
青木謙造は推理作家である。数年前、妻に先立たれて以来、孤独ながら気楽な独居を続けている。戦後、父が建てた北沢の邸はだだっ広く、至るところに闇を孕んで薄ら寒い。独り身の青木はすっかりこれを持て余している。書斎、寝室、台所。彼がふだん立ちいるのはそれぐらいだ。二階にはもう長いこと上がっていない。暮らし向きはごく簡素であり、生活には取りたてて何ごとも起こらない。たとえこの先、特筆すべき事件が生ずるにしても、おそらくそれは原稿のなかだけの出来事であろうと青木は思う。平和な退屈を抱えて、日々は穏やかに降り積もってゆくばかりに見える。
ところが今年に入って、たびたび書斎に「もう一人の青木謙造」が姿を現すようになる。始まりはひと月ほど前、世間の正月気分があらかた抜けきった時分である。深夜、坐椅子に坐って文机に向かい、スタンドの明かりだけを頼みに執筆を進めていると、ふいにそれはやってくる。
青木はヘビースモーカーだから、書斎には常に靄【もや】が立ちこめている。卓上スタンドと、背後の赤外線ヒーターが放つ光に白煙がたゆたう。その向こう、薄闇の奥の障子戸が音もなく開き、問題の人物はさも当然の権利のように、それでいてどことなく戸惑った様子で、そろりと室内に足を踏みいれるのだ。
普通なら、予期せぬ闖入者に驚倒し、何より先に身の危険を感ずるところだ。だが、初めてかの人物が現れた際、茫然としつつも妙に澄んだ心持ちで青木が抱いたのは、ああ、俺が来たぞ、という突飛な感慨だった。若いころに水泳をやっていたおかげで肩幅だけはある青木だが、全体的には非常な細身で、そのうえ恐ろしく背が高い。「もう一人の青木謙造」もまた、同様の体格をしている。所作のひとつひとつもよく似ているようだ。いや、それより何より、真に驚くべきはかの人物の容貌だ。にわかに信じがたいことだが、そこにあるのはまさしく青木自身の顔なのだ。
これが噂に聞くDoppelgangerというものだろうか? とっさにそう思ったのも無理からぬ一方、二人の上には明らかな外見の相違も認められた。それもそのはず、青木そっくりな「もう一人の青木謙造」の顔は、何とも不気味な鉄仮面で出来ていたのである。
鉄仮面。むろん本当の材質はわからない。いかにも重量感のある、艶のない鈍色【にびいろ】の仮面だ。それがすっぽりと頭部全体を包みこんでいる。逆三角形の輪郭に、いくぶん突出した尖った顎。頬骨がやけに目立つ。太い眉と、瞼の垂れた双眸。黒目の部分のみぽっかり孔が開いているのが仮面たる所以である。鷲鼻が印象的だ。唇はやや開き気味で、口もとの両側に深い皺が刻まれている。耳たぶのない両耳は、まったく青木らしい特徴を写し取って頭蓋に張りついており、正面からはほとんど視認できない。現実の青木と異なる点があるとすれば、豊かな頭髪を無造作に放置している本人に対し、仮面の頭がつるりとしていることぐらいだ。
それにしても、いくら酷似しているとはいえ、生身の顔と仮面はやはり別物である。にもかかわらず、青木がその男を(まず男に違いなかろう)自分自身だと感じたのには、服装の問題も少なからず影響していた。「もう一人の青木謙造」は、決まって青いロングコートを身に着けて現れるのだ。どうやらそれは、青木が大学時代に購入し、仲間内でひどく評判の悪かったコートと同じ品らしい。あまりに派手な色合いのため、一時は大教室の名物にまでなりかけた代物。毎日のように誰かしらに冷やかされ、半月ばかりで袖を通すのを止してしまった。かれこれ二十年も前の話である。
ともあれ、このような態【なり】をした「もう一人の青木謙造」が、或る日を境に頻繁に書斎に現れるようになったのだ。時間帯は真夜中に限られている。ただし毎日というわけではない。部屋が暗くないと出てこない。書斎以外では一度も見かけたことがない。青木が不在のときでも出現するのか、監視カメラでも設置しないかぎり、独り暮らしの青木には調べようがない。出てくるのは障子貼りの奥の引戸と決まっている。この障子戸の向こうは、狭い廊下が左右に伸び、左手の突き当たりに納戸があるばかりだ。では「もう一人の青木謙造」は、ガラクタだらけの暗い納戸からやってくるのだろうか。
書斎は畳敷きの八畳である。文机と、これだけは幅を利かせた書棚と、この家に負けず劣らず古臭く、骨董的価値もない衝立【ついたて】が置かれている。中央付近には、楕円形の小卓を挟み、肱かけ椅子が二脚向かいあっている。現れた鉄仮面は、衝立や肱かけ椅子をかろうじて避け、夢遊病者のごとき足取りで室内を徘徊する。そのさまが、当てもなく書店の棚を歩きまわる自分に似ているようだと青木は思う。もっとも、鉄仮面の徘徊はほんの一、二分に過ぎない。唐突に障子戸から侵入した彼は、やはり唐突に、今度はもうひとつの出入口である襖を開けて立ち去ってしまうのである。そのあと彼がどこに向かい、どこへ消えるのか、いまだに青木は知らない。毎度毎度、変に臆する気持ちが先に立ち、どうしてもあとを追うことができないのだ。坐椅子の上、咥え煙草の青木は、ただ手を束ねて、いかにもこの場に用はないといわんばかりの背中を見送るだけだ。
彼は思う。奴が俺に背を向けて出ていく……固唾を呑んでその後姿を見守っていると、俺は、あたかも自分自身がこの部屋を出ていく光景を背後から見つめているような気分になる。譬えるなら、「複製禁止」と題された、あのマグリッドの絵のようだ。これはじつに奇妙な感覚だ。いうまでもなく、俺は自分が青いロングコートを着ていないことも、ましてや鉄仮面など着けていないことも知っている。しかし実際のところ、少なくとも奴の後姿に目を向けているあいだ、俺は自分自身の姿を確認することができないのだ。ひょっとするとその数秒間の俺は、気づかぬうちにあの懐かしい青いコートを羽織り、すっぽりとかぶった鉄仮面の眼窩越しに、奴の様子を観察しているのかもしれない。そんなことはありえないと、どうしていえるだろう? この目で見ていない以上、確言などできようはずがないではないか。
そう……こうした不安を払拭する手立てもなくはない。奴の背中を見据えたまま、片手でいま着ているセーターの柔らかな手触りを確かめ、もう一方の掌で頬を撫で、素顔の皮膚を実感すればよい。ところが、ひとたび奴が現れると、そんなことはすっかり忘れてしまう。俺の意識は憑かれたように奴の存在に釘づけになってしまうのだ。
近所のホームセンターで早急に大きな鏡を買ってくるべきだ、と青木は思う。
いまとなっては、いちばん慌てふためくべきはずの最初の夜が、いちばん冷静でいられたわけだ。その後は、日を経るほどに心の安穏が不安と懐疑に置き換わってゆく。
何かの小説の書きだしに、これに類した出来事が記されていたはずだ。青木は遠い記憶をまさぐる。そして或るとき、水上勉の「短かい旅」という掌篇に行き着く。さっそく書棚から古い新潮文庫を引っ張りだしてみるものの、むろんそれで何が解決されるわけでもない。
あの男はいったい何者なのか?
なぜ仮面は俺と同じ顔をしているのだろう。
現実か、幻か。
奴はどこから現れ、どこへ消えるのだろう。
幽霊? それとも立体映像のようなものとは考えられないか。
青木は思う。例えば自分が死んだら、はたしてあいつは現れるだろうか、と。
そうこうするうち、思考の矛先は焦点を移していく。
よくよく考えてみれば、書斎に現れるかの人物が、鉄仮面をかぶり青いロングコートを着た「もう一人の青木謙造」であることが不思議なのではない。仮にそれが小学校時代の恩師だろうが、かつて行きつけにしていたバーの店長だろうが、あるいは見知らぬ誰かであったとしても……ふいに書斎に現れ、立ち去ってゆくという現象自体が不可解なのであり、鉄仮面は二の次の問題だ。とはいえ、謎を解明するには、かの人物の秘された素顔を暴いて真相を訊きだすのが最も手っ取り早い方法に思われる。
一度、気心の知れた知人に相談してみようと、青木は心に決める。
彼の手になる仮面をめぐり各地で事件が頻発する。
怪異とサスペンス、仮面づくしの連作短編ミステリ、連載開始。

前口上
吉祥寺駅の南口から井の頭公園を通り抜けて低い土手を上ると、碁盤の目に路地の入り組んだ品のよい住宅街が広がっている。住所でいうと、このあたりは三鷹市井の頭である。これを西へ向かえば、知らず識らずにまた広大な井の頭公園に呑みこまれることになり、所は武蔵野市御殿山と変ずる。一般に「武蔵野」の響きからイメージされる雑木林は、吉祥寺周辺ではこの御殿山の公園敷地内に美しい姿の大半を留めるのみだが、じつは吉祥寺通りをくだって自然文化園を過ぎた先の目立たぬ一角にも、丈高な雑木林の残る秘密めいた土地がある。
その小暗い木立のなか、いかにも人目を避けるような風情で、ささやかな洋館が潜んでいるのだった。白壁にフランス瓦の赤い三角屋根をいただき、周囲の環境も相まって、どことなく別荘然、四阿【あずまや】然として見える一軒家である。この淋しい家の存在を知る者は少ないが、さらにそこの住人、全身を黒衣に包み、鉄の仮面をかぶった異様な人物については、近隣の住民ですら見かけた者は稀であろう。
すこし前、藤江恭一郎という若き芸術家がいた。
知名度は低く、発表作品も多くないが、独特の個性を持つ仮面作家として一部で評価の高まりつつあった青年だ。
藤江が作品づくりに好んで用いた素材、それが鉄である。鍛鉄【ロートアイアン】。コークスを焚いて鉄を熱し、ハンマーで叩きのめし、火花を散らしてバーナーで焼き切る。やがて最後の工程において表面を埋め尽くす点描のごとき鎚目【つちめ】は、冷たく硬い鉄仮面に命を吹きこみ、あたかも人肌と見紛うほどの質感さえもたらすのだった。
仮面作家としての藤江恭一郎の活動期間はごく短かった。工房における不幸な事故が、彼の芸術家生命を奪ったのだといわれている。
ところで、蜃気楼のように姿を消したこの若き芸術家に関し、以前からまことしやかに囁かれている噂があった。
いわく、藤江恭一郎の手になる作品には呪いが籠められているとの一種の怪談で、いかにも眉唾ものの話だが、事実、彼の生みだした仮面にまつわる奇怪な出来事が、さまざまな場所でたしかにいくつも起こっていた。
第一話 訪問者
1
青木謙造は推理作家である。数年前、妻に先立たれて以来、孤独ながら気楽な独居を続けている。戦後、父が建てた北沢の邸はだだっ広く、至るところに闇を孕んで薄ら寒い。独り身の青木はすっかりこれを持て余している。書斎、寝室、台所。彼がふだん立ちいるのはそれぐらいだ。二階にはもう長いこと上がっていない。暮らし向きはごく簡素であり、生活には取りたてて何ごとも起こらない。たとえこの先、特筆すべき事件が生ずるにしても、おそらくそれは原稿のなかだけの出来事であろうと青木は思う。平和な退屈を抱えて、日々は穏やかに降り積もってゆくばかりに見える。
ところが今年に入って、たびたび書斎に「もう一人の青木謙造」が姿を現すようになる。始まりはひと月ほど前、世間の正月気分があらかた抜けきった時分である。深夜、坐椅子に坐って文机に向かい、スタンドの明かりだけを頼みに執筆を進めていると、ふいにそれはやってくる。
青木はヘビースモーカーだから、書斎には常に靄【もや】が立ちこめている。卓上スタンドと、背後の赤外線ヒーターが放つ光に白煙がたゆたう。その向こう、薄闇の奥の障子戸が音もなく開き、問題の人物はさも当然の権利のように、それでいてどことなく戸惑った様子で、そろりと室内に足を踏みいれるのだ。
普通なら、予期せぬ闖入者に驚倒し、何より先に身の危険を感ずるところだ。だが、初めてかの人物が現れた際、茫然としつつも妙に澄んだ心持ちで青木が抱いたのは、ああ、俺が来たぞ、という突飛な感慨だった。若いころに水泳をやっていたおかげで肩幅だけはある青木だが、全体的には非常な細身で、そのうえ恐ろしく背が高い。「もう一人の青木謙造」もまた、同様の体格をしている。所作のひとつひとつもよく似ているようだ。いや、それより何より、真に驚くべきはかの人物の容貌だ。にわかに信じがたいことだが、そこにあるのはまさしく青木自身の顔なのだ。
これが噂に聞くDoppelgangerというものだろうか? とっさにそう思ったのも無理からぬ一方、二人の上には明らかな外見の相違も認められた。それもそのはず、青木そっくりな「もう一人の青木謙造」の顔は、何とも不気味な鉄仮面で出来ていたのである。
鉄仮面。むろん本当の材質はわからない。いかにも重量感のある、艶のない鈍色【にびいろ】の仮面だ。それがすっぽりと頭部全体を包みこんでいる。逆三角形の輪郭に、いくぶん突出した尖った顎。頬骨がやけに目立つ。太い眉と、瞼の垂れた双眸。黒目の部分のみぽっかり孔が開いているのが仮面たる所以である。鷲鼻が印象的だ。唇はやや開き気味で、口もとの両側に深い皺が刻まれている。耳たぶのない両耳は、まったく青木らしい特徴を写し取って頭蓋に張りついており、正面からはほとんど視認できない。現実の青木と異なる点があるとすれば、豊かな頭髪を無造作に放置している本人に対し、仮面の頭がつるりとしていることぐらいだ。
それにしても、いくら酷似しているとはいえ、生身の顔と仮面はやはり別物である。にもかかわらず、青木がその男を(まず男に違いなかろう)自分自身だと感じたのには、服装の問題も少なからず影響していた。「もう一人の青木謙造」は、決まって青いロングコートを身に着けて現れるのだ。どうやらそれは、青木が大学時代に購入し、仲間内でひどく評判の悪かったコートと同じ品らしい。あまりに派手な色合いのため、一時は大教室の名物にまでなりかけた代物。毎日のように誰かしらに冷やかされ、半月ばかりで袖を通すのを止してしまった。かれこれ二十年も前の話である。
ともあれ、このような態【なり】をした「もう一人の青木謙造」が、或る日を境に頻繁に書斎に現れるようになったのだ。時間帯は真夜中に限られている。ただし毎日というわけではない。部屋が暗くないと出てこない。書斎以外では一度も見かけたことがない。青木が不在のときでも出現するのか、監視カメラでも設置しないかぎり、独り暮らしの青木には調べようがない。出てくるのは障子貼りの奥の引戸と決まっている。この障子戸の向こうは、狭い廊下が左右に伸び、左手の突き当たりに納戸があるばかりだ。では「もう一人の青木謙造」は、ガラクタだらけの暗い納戸からやってくるのだろうか。
書斎は畳敷きの八畳である。文机と、これだけは幅を利かせた書棚と、この家に負けず劣らず古臭く、骨董的価値もない衝立【ついたて】が置かれている。中央付近には、楕円形の小卓を挟み、肱かけ椅子が二脚向かいあっている。現れた鉄仮面は、衝立や肱かけ椅子をかろうじて避け、夢遊病者のごとき足取りで室内を徘徊する。そのさまが、当てもなく書店の棚を歩きまわる自分に似ているようだと青木は思う。もっとも、鉄仮面の徘徊はほんの一、二分に過ぎない。唐突に障子戸から侵入した彼は、やはり唐突に、今度はもうひとつの出入口である襖を開けて立ち去ってしまうのである。そのあと彼がどこに向かい、どこへ消えるのか、いまだに青木は知らない。毎度毎度、変に臆する気持ちが先に立ち、どうしてもあとを追うことができないのだ。坐椅子の上、咥え煙草の青木は、ただ手を束ねて、いかにもこの場に用はないといわんばかりの背中を見送るだけだ。
彼は思う。奴が俺に背を向けて出ていく……固唾を呑んでその後姿を見守っていると、俺は、あたかも自分自身がこの部屋を出ていく光景を背後から見つめているような気分になる。譬えるなら、「複製禁止」と題された、あのマグリッドの絵のようだ。これはじつに奇妙な感覚だ。いうまでもなく、俺は自分が青いロングコートを着ていないことも、ましてや鉄仮面など着けていないことも知っている。しかし実際のところ、少なくとも奴の後姿に目を向けているあいだ、俺は自分自身の姿を確認することができないのだ。ひょっとするとその数秒間の俺は、気づかぬうちにあの懐かしい青いコートを羽織り、すっぽりとかぶった鉄仮面の眼窩越しに、奴の様子を観察しているのかもしれない。そんなことはありえないと、どうしていえるだろう? この目で見ていない以上、確言などできようはずがないではないか。
そう……こうした不安を払拭する手立てもなくはない。奴の背中を見据えたまま、片手でいま着ているセーターの柔らかな手触りを確かめ、もう一方の掌で頬を撫で、素顔の皮膚を実感すればよい。ところが、ひとたび奴が現れると、そんなことはすっかり忘れてしまう。俺の意識は憑かれたように奴の存在に釘づけになってしまうのだ。
近所のホームセンターで早急に大きな鏡を買ってくるべきだ、と青木は思う。
いまとなっては、いちばん慌てふためくべきはずの最初の夜が、いちばん冷静でいられたわけだ。その後は、日を経るほどに心の安穏が不安と懐疑に置き換わってゆく。
何かの小説の書きだしに、これに類した出来事が記されていたはずだ。青木は遠い記憶をまさぐる。そして或るとき、水上勉の「短かい旅」という掌篇に行き着く。さっそく書棚から古い新潮文庫を引っ張りだしてみるものの、むろんそれで何が解決されるわけでもない。
あの男はいったい何者なのか?
なぜ仮面は俺と同じ顔をしているのだろう。
現実か、幻か。
奴はどこから現れ、どこへ消えるのだろう。
幽霊? それとも立体映像のようなものとは考えられないか。
青木は思う。例えば自分が死んだら、はたしてあいつは現れるだろうか、と。
そうこうするうち、思考の矛先は焦点を移していく。
よくよく考えてみれば、書斎に現れるかの人物が、鉄仮面をかぶり青いロングコートを着た「もう一人の青木謙造」であることが不思議なのではない。仮にそれが小学校時代の恩師だろうが、かつて行きつけにしていたバーの店長だろうが、あるいは見知らぬ誰かであったとしても……ふいに書斎に現れ、立ち去ってゆくという現象自体が不可解なのであり、鉄仮面は二の次の問題だ。とはいえ、謎を解明するには、かの人物の秘された素顔を暴いて真相を訊きだすのが最も手っ取り早い方法に思われる。
一度、気心の知れた知人に相談してみようと、青木は心に決める。