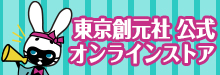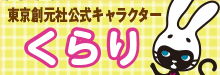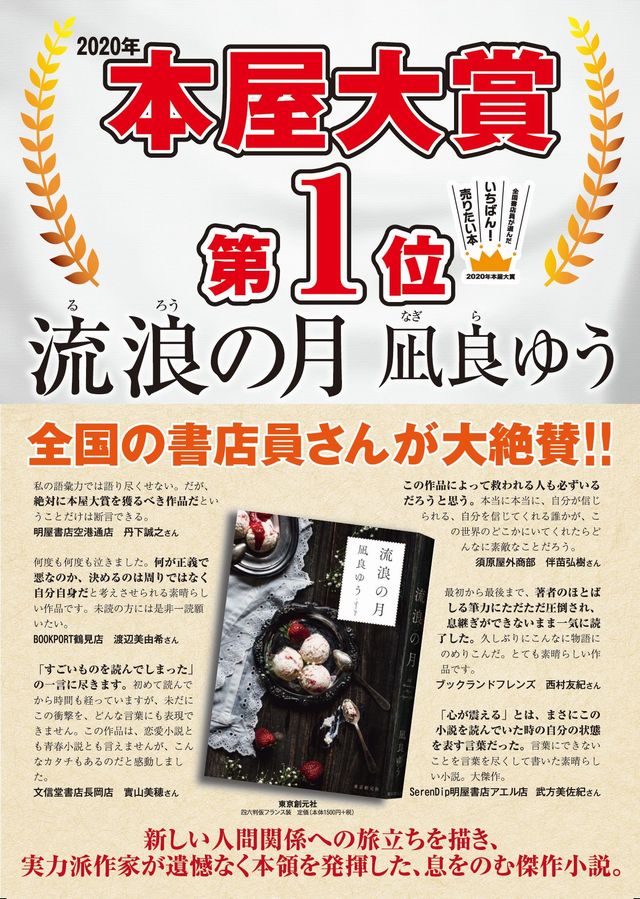12月13日
さて、そろそろこの仮面の告白も終わりが見えてきたようだ。
まだ俺には最後の一仕事が残されているが、その前に、もうじきこれを読んでくれるであろう青年のために、曖昧な点をできるだけはっきりさせておこう。
十年前の八月十二日、能登七海を殺したのは、白石光……つまり俺だ。
想像してみてほしい。
自分が殺した女の顔をかぶって生きつづける……これほど恐ろしい拷問がまたとあるだろうか?
では、なぜそんな状況に陥ったのか。
俺はかつて友であった男から強烈な復讐を受けたのだ。
どこまでわかりやすく書けるか心もとないが、順を追って綴ってみよう。
あの夏の日。稲村ケ崎の民宿。皆が寝静まった真夜中に、俺は能登七海を殺害現場となった空き小屋に呼びだした。部屋でビールを飲んで騒いでいたどさくさに、前もってメモ書きを渡しておいたのだ。おおよその内容はこんなものだ。
藤江から大事な話がある、往路通りすぎた小屋の前で、先に彼が待っていると。
つまり、七海ちゃんは藤江に会うために一人民宿を抜けだしたのだが、むろんメモの内容はでたらめで、藤江の与り知らぬことだった。
一泊旅行のすこし前から、藤江と七海ちゃんはなかなか深刻な関係に陥っていた。卑怯にも俺は、その機に乗じて自分の想いを七海ちゃんに伝えようとしたのだ。数か月間の秘めたる横恋慕……当然、あわよくばという魂胆があっての行動だ。
いまにして思えば、そんな姑息な手管を弄している時点で人の信頼を得られようはずもないが、当時の俺はとにかく彼女と二人きりになる場面を作ることに必死だった。何しろいちばん気づかれたくない相手は常に隣にいるのだ。東京に帰ってから、とも考えたが、ほんの些細なきっかけで彼らの仲が修復してしまう可能性は十分にあった。
高校からの親友を裏切ってまでことを為そうという思いつめた心理状態……あのときの俺が普通じゃなかったのはたしかだ。
俺が空き小屋に向かったのは七海ちゃんよりあとだった。彼女が出かけるのを確認する必要があったからだ。
月の射す夜道を急ぎ、小屋の前に着くと、藤江の姿が見えないのを不審に思ったのか、七海ちゃんが鍵のかかっていない扉を開けて小屋のなかを覘きこむところだった。
そこで俺は背後から声をかけ、粗末な小屋の前で、胸に渦巻いていた想いを不器用に吐きだした。
結果は誰しも想像がつくとおり、無残な敗北だった。憤然として彼女は来た道を戻りかけた。機嫌を損ねたまま帰らせるのは最も恐れていたことだ。俺はあわてて彼女を腕を掴み、我ながらどうするつもりだったのか……半開きの戸口から強引に小屋のなかに引きずりこんだのだ。
七海ちゃんは勝気な娘だった。力任せに手を振りほどくと、激烈な口調で俺を罵った。そのとき彼女が浴びせた手ひどい言葉……それをいまここに記すことはよそう。俺は頭に血がのぼり、発作的に彼女を突き飛ばした。七海ちゃんは短い悲鳴とともに転倒した。小屋の床は土間のはずなのに、妙に硬い音がした。壁ぞいにコンクリートのブロックが並んで埋めこまれているのに気づいたのはあとになってからだ。
我に返ると、俺は森閑とした暗がりのなかに一人立ち尽くしていた。
倒れた七海ちゃんは呻き声も上げなければ身動きもしなかった。
気が動顛していた俺はとっさにその場から逃げだした。脇目も振らず民宿まで戻り、一度は部屋の布団に身を横たえたのだが……どのぐらいそうしていただろう、十分か、二十分か、ようやくいくらか冷静を取り戻して、さすがにこれはまずいと思い直し、夜道を小屋まで引き返すことにした。じつはこのとき、目を覚ました早見篤がただならぬ俺の様子を怪しんでこっそりあとを跟けてきていたのだが、のちに声をかけられるまで気づきもしなかった。
ふたたび足を踏みいれた小屋では最悪の事態が待っていた。暗がりの土間、仰向けの状態で、七海ちゃんはすでにこと切れていたのだ。そればかりでない。倒れた彼女の傍ら、薄色の壁板に何やら文字らしきものが書いてあるではないか。
小さな窓から朧な月明かりが射していた。七海ちゃんの横で屈みこんでいた俺は、すぐにそれを見つけてギョッとした。念のため携帯電話のライトで照らしたところ、黒っぽい文字は明らかに血で書かれたものだった。七海ちゃんは運悪くコンクリートブロックに後頭部を打ちつけており……命の灯が消える直前、みずからを死に至らしめた加害者の名を記したのだ、黒髪をねっとりと濡らした鮮血で「白石光」と。
突然、何をしてる、と低い声がして、跪いた俺は驚きのあまり尻餅を突いた。
戸口に佇んだ黒影の主は早見篤だった。
どう言い訳してもごまかしようのない状況だった。俺は茫然自失のまま、何者かに操られているかのごとく事情を話し、それから、もうおしまいだといって泣いた。
早見は無言で七海ちゃんの遺体を検め、板壁に滲【し】みこんで早くも乾きかけている俺の名前を見つめて、これを消すのは無理だな、といった。
殺すつもりはなかった。あらゆることが悪いほうへ働いたのだ。まったく魔に魅入られていたとしかいいようがない。何もかも終わったと思った。数分ののち、早見はすべてを皆に告げるだろう。俺は観念し、絶望した。
ところが、次に早見が発した言葉は思いもよらぬものだった。
白と黒……、と奴は独り言のようにつぶやいた。そして、こいつは面白い。おい、何とかなるかもしれないぜ、と妙に活き活きとした調子でいったのだ。
早見篤というのは聡明ではあるが自信過剰の皮肉屋で、もともと俺はあまり奴を好いてはいなかった。態度の端々から向こうも薄々気づいていたに違いないが、そんな男が窮地に追いこまれた俺に協力を申し出たのは、意外というほかなかった。
白と黒。わずかの時間に早見が捻りだした奇想。奴は壁に書かれた「白石光」という文字を、「黒百合番太郎」に書き替えるというのだった。
「黒百合番太郎」……それは高校時代に藤江恭一郎が舞台に立ったときの芸名だ。その際の衣裳……鉄仮面と黒衣を藤江が旅行に持参していたことが早見に着想をもたらしたのだろう。それにしても頭のいい男ではある。
藤江に罪を着せるのか? 情けない涙声のまま俺は訊いた。
早見はいった。
いささか説得力には欠けるが、あいつには……いや、あいつにだけは動機があるじゃないか。しかし、嫌なら止めてもいい。俺は宿へ戻って洗いざらいぶち撒けるまでだ。
奴の声は闇が発するささやきだった。そうして結局、俺はこの恐ろしい提案に乗ったのだ……。
腑抜けになった俺の目の前で、早見は死者の指を使って巧みに壁の文字を作り替えた。鮮やかなものだった。幸か不幸か元の文字はいびつに乱れており、少々の不自然さは気にならなかった。
それにしても、ダイイングメッセージに細工を施したぐらいではとても安心はできない。が、早見の悪魔の脳髄は、ちゃんと次なる一手も考えていた。演劇マニアだった奴は、唐突に以前観た舞台の話を始めた。それは一見場違いとも思えるこんな話だった。
親子三人の朝の食卓、卓袱台の向こう正面に父親が坐っている。大きく広げた新聞のせいで、客席から彼の上半身は見えず、ただ声だけが聞こえている。やがて、いつまで経っても食事に箸をつけない夫に腹を立てた妻が新聞を取り上げる……と、なんとその男には首がないのだった……。
ナンセンスコメディのドタバタ劇とのことだったが、仕掛けはこうだ。夫役の俳優は肩幅の「あんこ(かさ増しのための補強材を演劇用語でそういうらしい)」で頭部を左右から挟みこみ、それを包む大きな衣装を着ているのだ。要するに実際の頭の上に作りものの肩があるというわけだ。この場合、腕の生える位置が多少おかしなことになるけれど、そこは衣裳のデザインでカバーしていたという。それと似たようなことをやろうと早見篤はいうのだった。
何でもいい、とにかくあり合わせの衣類を紐で縛って型を作る。かつて奴が舞台で観たものとは違い、今回の型には贋物の頭も付いていて、そこに藤江恭一郎の持ってきた鉄仮面をかぶせるのだ。その上から藤江の長身に合わせた丈長の黒衣を着こめば、上手い具合に藤江と同じぐらいの背丈をした仮面の怪人物が出来上がるという寸法だ。むろんこれでは前が見えないが、黒衣の胸もとを目立たぬように裂いておき、そこから視界を確保する。
俺たちは足を忍ばせて宿の部屋に戻り、計画を遂行した。その脇で藤江はぐっすりと熟睡していた。
早朝五時、早見の指示で、俺は突貫作業の扮装をまとってひとしきり海岸通りをさまよい(浜辺にはすでにサーファーたちの姿があった)、ふたたび部屋に戻って仮面と黒衣を藤江のバッグに戻すと、何ごともなかったかのように布団に入って時を待った。薄闇のなか、隣で早見の目が悪戯っぽく笑っていた……。
やがて六時半ごろ、別部屋の女子が戸を叩き、七海ちゃんの姿が見えないことを告げた。
すべては目論見どおりだった。ほどなく一同で捜索が始まり、その過程で仮面の男の目撃談が飛びこんでくる。思いもよらぬ場所、古びた空き小屋のなかに変わり果てた少女の姿を見出すまでにはいくばくかの時間を要した。
そこから先は、やはり目論見どおり藤江恭一郎の身に嫌疑が及び(不運なことに彼には夢中遊行の奇癖もあったのだ)、この罪のない友は、以来二重の苦しみを舐めつづけることになったのだ。
能登新月くん。
以上が十年前の事件の真相だ。
君の姉さんを殺したのは俺だ。白石光だ。
その晩の一連の行為、あれは本当に俺自身がやったことなのか? どうにも不思議で仕方がない。あれは若さゆえの過ちであったと思う。だが、そんな言い訳が通用しないのは百も承知だ。
俺は悪魔に魂を売り、友を裏切り、のみならず、その後も親友の仮面を着けて彼に同情を示し、励ましつづけたのだ。
それでも過去が時の彼方に封印されてしまったなら、俺は鼓動を止めた心臓を胸に収めたまま、いっさいを割り切って血の気のない顔で平和に暮らしていたかもしれない。ところがそうそう上手くはいかないものだ。
この一件からほどなくして、以降十年間にわたる早見篤の恐喝が始まったのだ……。
大学を中退した藤江は、持ち前の才能を如何なく発揮して芸術家となった。けれども運命は彼にさらなる試練を与えた。工房での爆発事故……やがて藤江は忽然と俺の前から姿を消した。
彼がこの邸に棲んでいることを知ったのは今年の九月だ。或る日、俺は彼から一通の手紙を受け取った。
それは文字どおり俺を地獄へ突き落とす復讐の一太刀だった。事故による長期入院のあいだに、ついに藤江は遠い悲劇の真実に到達したのだ。細部こそ想像の追いつかぬところはあったものの(細部……早見篤の関与が抜けていた)、彼はほぼ真相をいい当てていた。
手紙の一部をここに抜萃しておこう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(前略)
あの夏の海辺で、誰が能登七海を殺したのか。それともあれは事故だったのか。
長い時間が過ぎたいまになって、僕には悲劇の真の形がよく見える。
白石、もちろん君は先刻ご承知だろう。
ダイイングメッセージ……そう、能登七海はたしかに己の血で犯人を名指ししたのだ。
君にはわかるはずだ。君にだけはわかるはずだ。
黒百合番太郎。白石光。
闇に射す太陽。黒のなかの白。
この数枚に及ぶ手紙とは別に、僕は君にちょっと風変わりな贈りものをしておいた。いずれそれを手にしたとき、君はその意味するところを理解してくれるはずだ。
答えは出たのだ。
いわば君は出題者であり、僕は回答者……否、告発者、復讐者だ。
あの日起こったことを、いまから僕なりに説明してみよう。
なかなかよく考えたと感心してくれたらいいのだが。
(中略 ※ここで事件についての推理が披露されている)
白石、僕は死を選ぶことに決めたよ。
昨年、敬愛すべき老音楽家が死出の旅路についたこの家、この部屋で、僕もまた同じ道を行くのだ。
もうじき主【あるじ】不在となるこの家だが、かねてのご要望どおり、君には僕の身代わりとなってここで暮らしてもらおうと思う。それは君自身が望んだこと……よもや忘れてはいまいね?
或るとき、君は僕にこういった。「お前はずいぶん不幸な目に遭ったが、それでもお前には芸術があるじゃないか。これは激励なんかじゃない。俺はお前がそんな無残な姿になったいまでも、お前のことがうらやましいのだ。叶うなら取って代わりたいとさえ思う」と。
吉祥寺の工房での事故のあと、長い入院期間に、僕は君を自分の身代わりに仕立てる方法を考えていた。むろん深い意味はなかった。暇つぶしのよしなしごとだ。だが、僕はそこで気づいてしまったのだ。あの事件の夜、僕を陥れるために君が弄したトリックについて。それは先ほど克明に記したとおりだ。
白石、僕は思い出を懐かしむために七海の仮面を拵えたのではない。ましてや、僕が死ぬのは顔面に負った惨たらしい傷のせいなどではない。僕は、長いあいだ友と信じて疑わなかった男に裏切られたがため……その裏切りの、想像を絶する残酷なやり口に絶望するあまり、世を儚んでみずから命を絶つのだ。
白石、お望みどおり君には今後「藤江恭一郎」として人生を送ってもらう。
そのために用意した君への贈りものが、すでにいま目の前の机に載っている。一目見て、君はすべてを諒解するはずだ。僕が本当に十年前の事件の真相を見抜いてしまったことも、自分がそれをどう活用すべきなのかも。
むろん選択権は君にある。ただし忠告したいのは、もしも僕の死亡が確認されるか、その家から僕の姿が消えて或る一定期間を経過した時点で、いっさいを暴露する封書が開封される手筈になっている。その作業はとある弁護士事務所で速やかに行われるだろう(大人になって、その程度の智恵は僕も身につけたのだよ)。
拘束期限は君の寿命が尽きるまでだ。君は死ぬまで「藤江恭一郎」としてこの雑木林のなかの一軒家で過ごすか、それともどこかに別の道を見出すのか……その決断の仕方が甚だ興味深いところではある。もちろん、刑事罰の時効はいずれ訪れるだろう。だが、「法に問われぬ殺人者」の烙印を背にのうのうと生きていく勇気が、はたして君にあるだろうか……。
これから君がしなくてはならないことを伝えよう。
まずは天井からぶら下がっている僕の死体を下ろしてもらう。それから僕の顔を覆っている鉄仮面(君が殺した女の顔だ)を外し、机に置いてある君への贈りものに装着してほしい。サイズはぴったりに作ってある。
次に君は、僕の死体を裏庭に埋めなくてはならない。僕をこの世から消し去ることで、初めて君は僕になり遂せるのだ。これを読み終えたあとで裏庭へ行ってみるといい。非力な君のため、ちゃんと埋葬の穴を掘っておいてあげた。君が「藤江恭一郎」としてここにいるかぎり、僕の死体が見つかる気遣いはないだろう。
ここまで済んだらあとは自由だ。「藤江恭一郎」として、好きに暮らすがいい。もう一度、芸術の道に励むのもいいかもしれない。もっともその場合は、相応の作品を作ってもらわないと僕の評判が落ちる。心してくれ。
何しろ急な話だから、当面は白石光と「藤江恭一郎」、二重の生活を強いられると思う。だが、なるべく早く君は「藤江恭一郎」になりきらなくてはいけない。その方法は君に任せる。早晩、白石光のほうには会社を辞めてもらい、そのまま海外にでも移住してもらうのがいいんじゃないか。ようく考えて巧くやることだ。
健闘を祈る、白石光くん……否、「藤江恭一郎」くん。
死せる藤江恭一郎
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
さあ、あまり悠長にしてもいられない。ここからは駆け足で進めよう。
藤江恭一郎の遺書に命ぜられるままに俺はこの邸を訪れた。そして、若き芸術家の縊死体を発見し、彼の手になる奇抜な贈りものを受け取ったのだ。それが何であるか、君にはもう想像がついているだろう。十年前に俺と早見が慌てて拵えたもの……つい先日、早見篤が「影百合」に化けるのに用意したもの(あの怪人の正体は早見だ)……チビの俺が「藤江恭一郎」となるための「長身具」が、これ見よがしに机の上に置かれていたのだ。さすがは芸術家だ。それはまるで一個の商品のように滑らかにプラスティックを成形してあった。
もはや逃げ道はなかった。藤江のいいなりに動くか死ぬかの二者択一だ。
俺は適当な理由をつけて勤め先の出版社を辞める手筈を調え、時に白石光として、時に仮面の「藤江恭一郎」として、後者に完全移行するための準備を始めた。その過程では、先々の予行演習のつもりで、知人(担当していた老作家)の前に「長身具」を装着した姿で現れたりもした。是璃寓で君と出会ったのもそんな時期だったのだよ。
能登新月くん、俺は死せる芸術家から復讐を受けたが、当然彼だけでなく、君からも同様に復讐さるべき男だ。それから、何を措いても君の姉さん、少女のまま生涯を閉じた七海ちゃんから最も重い罰を受けなくてはならない。
俺は一度は君を殺そうとした。すまなかった。だが、葬るべきは君ではないと危ういところで気がついたのだ。
ゆうべ、早見篤が血相を変えてここへやってきた。死んだはずの君が写真館へ現れたという。前の晩(君が写真館を訪ねた日)に電話があったが俺はしらばっくれていた。しらばっくれて、奴がここへ来るのを待っていたのだ。
能登くん、いま君がいる部屋の隅に、ソファやテーブルが寄せてあるだろう。早見篤の醜い死体はその陰に横たわっている。学生時代、そして社会に出てからも、俺があの男にどれだけ毟り取られてきたか……自業自得といわれてもかまわない、俺は俺でひとつの復讐を成し遂げたのだ。
この手記を書き終えたら、俺はここからいちばん近い公衆電話まで出かけて君に電話をするつもりだ。ぜひもう一度、ここへ来てほしい。君ならきっと来てくれると信じている。
今夜はあいにくの雨模様だ。冷たく濡れた体で君がこの部屋の扉を開くころ、俺はもうこの世にはいない。君は机に置かれた奇抜な「長身具」を見つけ、この手記を読んで、すべてを知るだろう。早見の車はとある場所に移動させておいたが、一日帰らないことでそろそろ騒ぎになりはじめているかもしれない。一刻も早く君がこれを読んでくれることを祈らずにはいられない。
いま俺の手もとに残されたもの。
鉄仮面、黒衣、「長身具」、藤江恭一郎の遺書、君が工房からくすねてきた写真、それから……。
面白い話がある。
昔読んだカミュの『異邦人』、その文庫本の解説にこんなことが書いてあった。主人公ムルソーの名は、「死(Mort)」と「太陽(Soleil)」の合成ではないかというのだ。
その伝でいけば、さしずめ白石光は「白い光」……いわば太陽であるが、いかにもこれは俺の人間性にそぐわない。むしろ白石を「白い死」とでも読み変えたほうが似合いのようだ。
一方、能登新月……不可視の月をその名に持ちながら活き活きと明るい君は、俺よりずっと太陽らしい。
こんな言葉遊びを別辞として、俺は君にこの仮面の告白を託すとしよう。
読み終えたら警察へ連絡してくれたまえ。
さようなら、新月くん。
そして、友よ、いつ何時もわが傍にあり、最後の最後まで離れることのなかった親しげな友、「孤独」よ――。
さようなら。
お前だけに見守られながら、俺は道を外れてしまった憐れな人生に終止符を打つ。
*
電気スタンドの明かりで手記を読み終えた能登新月は、肱掛椅子から立ち上がると、ぼんやりと黝【くろず】んだ部屋の奥へ向かい、ソファの陰に転がった眼鏡の男の死体を確かめた。
それから中央へ返し、足を止めると、天井からぶら下がった縊死体を見上げた。黒衣の裾は胸もとあたりまで垂れていたが、おそらく内側の爪先はだいぶ上にあるだろう。死体は、作りものではない自身の顔に鉄仮面を着けて首を縊っていた。仮面は美しい少女の顔をしていたが、空洞となった両の黒目は、あたかも次なる生贄を待つように、虚ろにこちらを見下ろしていた。
新月はまた机の前まで行って、白石光いうところの「長身具」を両手で捧げ持った。のっぺらぼうの白い顔が目の高さにある。本来、鉄仮面はそこに装着されているべきなのだ。気味の悪い作業になるが、どうにかして縊死体から仮面を外さねばならないと思った。
彼はいったん死体を振り返り、ふたたび両手に抱えた妙ちきりんな物体を見つめた。
仮面。黒衣。奇抜な「長身具」……変身の種はすべてそこにあった。
暗い雑木林の奥に潜む、恐ろしく背の高い黒衣の鉄仮面。
狂気を宿し、人々の惧れと好奇の目のなかを、美しい十七の少女の笑みを湛えて徘徊する、謎の芸術家……。
薄明かりのもと、ふいに新月は打ち震えた。若き猟奇の徒の滑らかな頬は徐々に火照りはじめ、爛々と耀きだしたその双眸は、見る間に怪しげな潤みを帯びてゆくのだった。
(完)
続きを読む